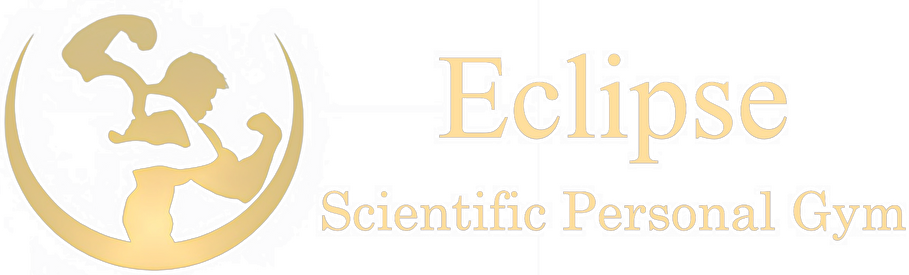筋力の発揮限界
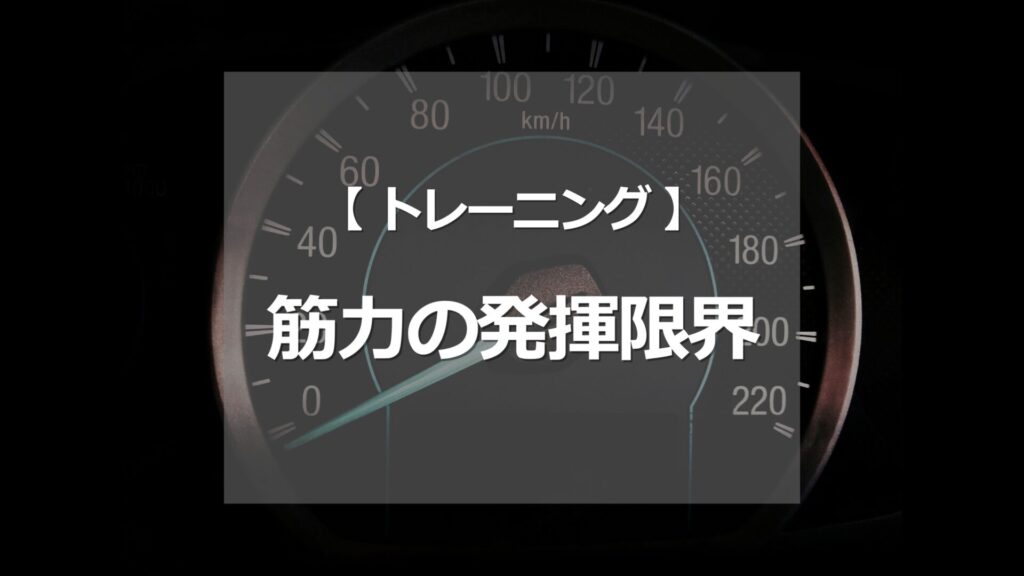
筋力の発揮限界には、生理的限界と心理的限界があります。
生理的限界は筋肉が発揮できる理論上の最大値を指し、心理的限界は筋力発揮における心のリミッターです。
筋力発揮の生理的限界
以前、筋力の発揮についての記事を書きました。
ここでは筋力発揮を[ 筋の動員数×筋の生理学的横断面積 ] で説明しました。
筋力の生理的限界とは、後者の筋肉そのものが持つポテンシャルを指します。
筋力発揮の際には、その必要に応じて動員数が選択されており、すべての筋肉が活動しているわけではありません。
また自身が最大努力で取り組んでいると思っていても、すべての筋肉が動員されるということはありません。
筋力の生理的限界は、そういった使用制限を取り払った、筋肉が発揮し得る最大値を指します。
具体的には、電気を流してすべての筋肉を活動させて測定することが可能です。
筋力発揮の心理的限界
心理的限界とは、意識的に発揮できる筋力の限界値を指します。
人間は全力を出しているつもりでも、実際のところ筋肉には余力があります。
これは人体に備わったリミッター機構であり、過剰な筋力発揮で周辺組織を損傷させたり、エネルギーを無駄に消耗させないように作られた仕組みとされています。
事前の訓練なく人体の筋力を100%で出力しようものなら、その体は出力に耐えきれず何かしらの故障を起こします。
また高度に訓練を積んだ人の中には、外力も相まって生理的限界を超えてしまい、骨折などを引き起こした事例もあります。1
リミッターとはそういうものです。
この心理的限界によるリミッターはかなり低い位置に設定されており、練習やトレーニングを重ねていくことで、少しづつ生理的限界に近づいていきます。
トレーニングによる適応
筋力トレーニングを重ねていくと、筋肉自体が適応(発達)することで生理的限界の上限は引き上げられていきます。
またトレーニングを重ねていくにつれて心理的限界の上限も引き上げられ、生理的限界に近づいていきます。
体は何度も限界(と思っている)状況に追い込まれることで、「ここはまだ限界ではない」と認識が更新されていきます。
これが神経系のトレーニングであり、筋の動員数が向上することで筋力発揮が向上していきます。
心理的限界の個人差
心理的限界は、上記の通り神経系の適応といった、バイオメカニクス的な観点から語られることも多いですが、個人のメンタルももちろん影響します。
筋トレで疲労困憊まで追い込めて、客観的に見れば十分だろうと思えるほどであっても、さらに自信を追い込む狂人もいます。
対して気持ちはあるものの、筋肉が疲労困憊を迎える前に、心が折れてしまう人もいます。
生物が環境適応のための多様性として獲得した気質の差であるので、どちらが良いとかはありませんが、追い込める方が筋トレには有利ではあります。
追い込むのが苦手な場合の戦略として、セット数や頻度を増やすという手段があります。
筋トレ効果の要諦は総負荷量ですので、重量×回数による追い込みが難しくても、他でカバーしてしまえば問題ありません。
まとめ
トレーニングとはこの限界値を引き上げていく訓練です。
稀にリミッターが壊れたおかしな人がいますが、それは同時にリスクも伴っています。
競技的には有利かもしれませんが、将来の生活に差し障るような怪我に繋がらないことを祈っています。
- パワーリフターがスクワット時に両足骨折したり、ボディビルダーがレッグプレスで剥離骨折(大人では滅多になりません)したり。 ↩︎