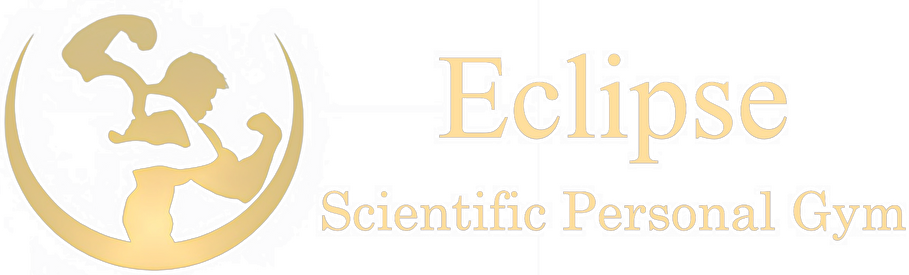筋トレ全身法を試してみた
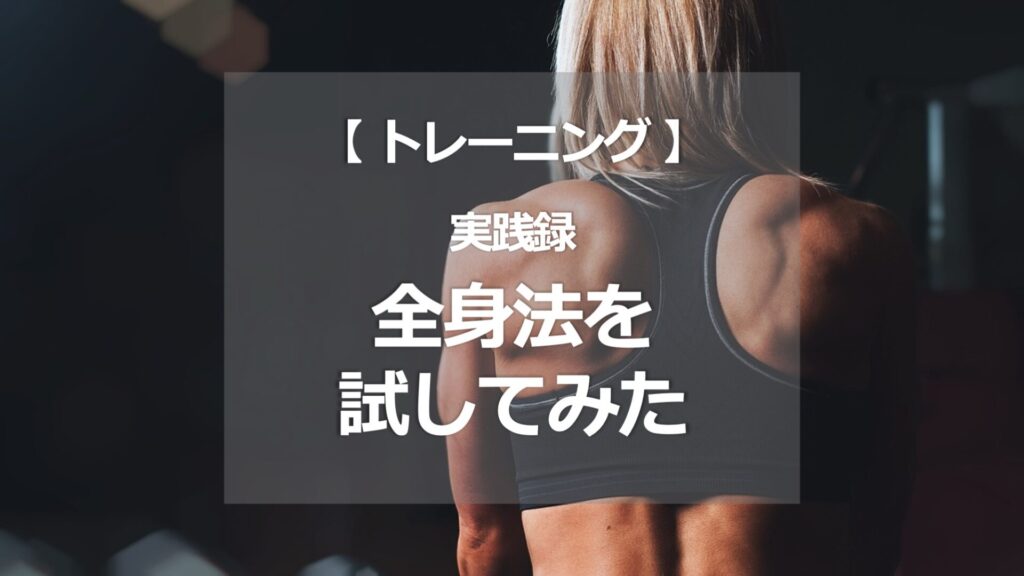

トレーナーの首藤です。
今回は研究論文ではなくただの実践結果レビューです。
Eclipseの開業までおよそ1ヶ月ありました。
トレーニング環境も変わりましたので、その間トレーニングも変えてみようと思い、分割法より効果が高いと噂の全身法に切り替えてみることにしました。
日本トップのボディビルダーたち誰もやっていないけど、本当に全身法の方がいいのか?
結論
- トレーニング頻度やレベルによっては良い
- 筋トレ上級者には向かないかも
- 総負荷量が分割法を超えるかが要諦
最後にトレーニングレベル別に考察してみます。
はじめに言っておきますが、ノリで始めたことだったので、まともな検証ではないです。
個人の所感ですので、参考程度に捉えてください。
前提
近年、筋肥大には全身法がいいよ、って論文が結構出てきています。
代表論文として著名なSchoenfeld氏を引用1
分割法でやるより全身法でやったほうが筋肥大したよ、って話です。
また以前コラム掲載した通り、筋肥大にはトレーニングの総負荷量が重要となります。
そして筋肉痛になるかは筋肥大には重要ではなく、また超回復の理論も実際はよく解明されていない。
筆者はトレーニング歴7年くらいで、ずっと4または5分割法でやってきており、週5以上はトレーニングをしています。
それをやめて全身法に変えてみたらどうなるのかな、という実践です。
ちなみにプチ減量中で体重は1ヶ月で変わらないか若干落ちているかといった感じでした。
前提
- どうやら分割法より全身法の方が筋肥大するらしい
- 筋肥大は総負荷量による
- 筋肉痛はなくていいし、超回復理論は一旦無視する
- まあまあトレーニング経験があり、プチ減量中
方法
考えるのが面倒だったので、
あまり変数を入れない方がいいと思い、ルーティンを縦割りしました。
元々は4分割のルーティンです。(脚 → 胸 → 背中 → 肩)
それを縦に4分割して毎日全身動かすようにしました。
合ってんのか、この手法で?
腹筋など一部省略していますが、元々は下記のような内容でした。
脚
- スクワット
- ルーマニアンデッドリフト
- ベルトスクワット
- ヒップスラスト
- カーフレイズ
胸
- ベンチプレス
- ダンベルプレス
- インクラインベンチプレス
- インクラインダンベルプレス
- ダンベルフライ
背中
- デッドリフト
- チンニング
- ラットプルダウン
- Vバーラット
- プルオーバー
- ワンハンドロウ
- ローロウ
肩
- バックプレス
- ダンベルショルダープレス
- サイドレイズ
- ワンハンドサイドレイズ
- インクラインサイドレイズ
- アップライトロウ
- フェイスプル
ここから各部位3つに分割して、それぞれをズラして組み合わせます。
便宜上全身法とは言いましたが、完全に毎日全部やっているわけではありません。
BIG3の前日は対象部位のオフをとる形にしました。
A
- スクワット
- ルーマニアンデッドリフト
- ワンハンドロウ
- ローロウ
- アップライトロウ
- フェイスプル
B
- ベンチプレス
- ダンベルプレス
- ベルトスクワット
- ダンベルショルダープレス
- サイドレイズ
- ワンハンドサイドレイズ
C
- デッドリフト
- プルオーバー
- インクラインベンチプレス
- インクラインダンベルプレス
- ヒップスラスト
- カーフレイズ
D
- バックプレス
- サイドレイズ
- インクラインサイドレイズ
- チンニング
- ラットプルダウン
- Vバーラット
- ダンベルフライ
レップ数とセット数は分割法の時と同じようにしています。
重量は、伸ばせるものは伸ばしていきます。
レップとセットが同じでも、重量が伸びれば総負荷量は伸びます。
これにより週当たりの総負荷量が分割法を上回れるのかがポイントです。
結果
結果を良かった点、微妙な点、良くない点でまとめます。
良かった点
- 総負荷量は稼げる
- 筋肉痛はあまり影響しない
- 部位別種目が少なくて集中できる
一番メリットを感じた点は、分割法で後半に配置されていた種目の使用重量が伸びたことです。
伸びたと言うよりも、疲れていないからできるだけなのですが、使用重量が向上したことで総負荷量を増やすという狙いは達成されました。
連日で同じ部位を刺激するので、筋肉痛の影響はないかと懸念はありましたが、1日2種目くらいでは翌日のトレーニングが出来なくなるほどの筋肉痛が来ることはありませんでした。
もちろん筋肉痛が全くないわけでもないですし疲労感は常にありましたが、出来ないことはないです。
基本的に各部位がある程度元気なので、重量も使えて集中はできます。
微妙な点
- そうは言っても後半はキツい
- 追い込み感は大きくない
- 疲労管理が難しい
とはいえ最大努力で各部位をやっていくわけですから、後半はキツいです。
重量は扱えるわけですから、後半になってもずっと全力を出さないといけないです。
それから後半の「追い込み感」みたいなのはないです。
対象部位がオールアウトしてる感じはなく、ただただ全身どんよりとキツいです。
(まあそもそもその「追い込み感」は自己満足でしかなく効果は低いという理論もあるんですが……。)
そして結果的に総負荷量が増えたからなのか疲れが残りやすく、疲労管理が分割法より難しく感じました。
オフを取るべきなのかの判断に迷う日が多々あります。
分割法であれば対象部位の疲労感や腰部などのハリで判断できるのですが、後述する通り腰はずっと張っていました。
良くない点
- SQ/DLの使用重量は落ちる
- 腰部&脚部疲労が抜けにくい
- オフが余計に必要になることがある
- 無駄に戦略性を要する
- 毎日脚トレはちょっと勘弁してほしい
減量の影響もあってか、スクワットとデッドリフトの使用重量は落ちました。
レップとセットである程度のボリュームは確保できているので良いんですが、少し凹みます。
パワーリフターのように、計画的に疲労をコントロールするプログラムを組んでいないこともあるかと思います。
毎日のように高重量が足腰にかかってくるので、腰部と脚部の疲労は抜けにくいです。
分割法では胸と肩の日であれば、足腰のリカバリーに当てられていたのですが、毎日のように足腰を使ったトレーニングが入るので当然と言えば当然の結果です。
そうなると余計にオフをとる必要が出てきました。
とりわけ1ヶ月実践の後半では、週5回のトレーニングがギリギリな感じになりました。
分割法であれば週6か週7で回せていたので、そう考えると1週間当たりの総負荷量は分割法を下回っているのでは? と懸念が出ました。
上記のように、結構な疲労管理が必要になり、プログラム作成でもオフの取り方でも、分割法より高い戦略性を必要としました。
そして何より、毎日脚トレがあるのは心理的にもキツいのです。
考察
すでに結果のところで考察っぽいこともしているのですが、そこから生じた所感的なものです。
最初からそうでしたが、ここから先はさらに根拠がありません。
根拠なくする考察
- 分割法の方が疲労管理戦略がシンプルでやりやすい
- 上級者は分割法の方がむしろ理に適っているのでは……?
- 週3,4回以下のトレーニングなら全身法のがいいかも
- ホルモン分泌の観点では、たくさんの筋肉を動かせる全身法がいいかも?
しかしメタボリックストレスが不足するから……?
先に引用したSchoenfeldの論文も、毎日トレーニングとかするタイプの研究ではないんですよね。
(週3回のトレーニングとかの研究です)
そこの前提が違うのに、全身法で毎日トレーニングしようとすると、私のように疲労管理に苦戦することになりそうです。
プログラムの設計からオフの取り方やタイミングまで、戦略的なトレーニング設計が必要となります。
そうなると、生活もある程度その戦略に沿わせる必要があるというか。
仕事でやむを得ずオフ、とか、調子がいいから連日トレ、とかはやりにくいでしょう。
そんな戦略を考えながら総負荷量は分割法を上回っていかないといけないわけです。
もうトレーニングレベルがある程度あって毎日トレーニングする人は、分割法のほうが理に適っているのでは?
疲労管理の観点も含めて、無駄な戦略を立てるよりもシンプルでいい気がします。
ただ週3,4回以下のトレーニングとかなのなら、分割するよりも全身法のほうがリカバリーと総負荷量のバランスが良くなりそうです。
その頻度なら、やり方によっては分割法のほうがボリューム落ちることもありますから。
なんなら初級者はしばらく全身法でもいいでしょう。
分割して各部位を徹底的に追い込めるのは、まあまあ練度の高いトレーニーです。
ホルモン分泌の観点からは、どっちも言えるかな〜と思います。
たくさんの筋肉を動かせる全身法のほうが、ホルモン分泌はたくさんできる気もします。
一方でメタボリックストレス、つまりパンプ感やバーン感などの筋内環境悪化による生理学的応答は分割法のほうが得られやすそうです。
どっちがいいかの判定は学者の研究結果を待つということで…..。
後出しっぽくはなるんですが、総負荷量を揃えれば分割でも全身でも結果は一緒なんですよね。2
本件の要諦は、分割法と全身法ではどちらが週当たりの総負荷量を確保しやすいか、です。
段階別のオススメ
以上を踏まえて、トレーニングレベルに合わせたオススメ方法を記して、まとめとします。
段階ですが、トレーニングを始めて何ヶ月、とかはあんまり指標にならないので、自分のレベルは胸に手を当てて自分で考えてください。
初級者
全身法がオススメ
オールアウトにたくさんの種目が必要なほど筋肉量がないので、全身しっかりトレーニングして回復させてを繰り返すほうが良いです。週2,3回の全身法で十分でしょう。メニューも毎回同じで大丈夫です。ベーシックな種目を選択し、フォームに気をつけながら重量を少しずつ伸ばせれば良いです。
中級者
どちらかなら全身法がオススメ
筋肉量も付いてきて、使用重量も伸びてきた頃です。週4回以下のトレーニングであれば、パターン化した全身法を組むと良いでしょう。胸の上部・中部・下部、肩の前部・側部・後部のように、細分化した種目を組み入れていきます。この時、疲労がどこに溜まり、次はどの部位を使うのかなどを考えながらプログラムを組んでいきます。週5回以上のトレーニングをするのであれば、分割法に移ってもいいですが、5分割以上の細かい分割は結果的に週当たりの総負荷量を減らす可能性があることを念頭に置いておきましょう。
上級者
どちらかなら分割法がオススメ
筋量・筋力ともに向上しており、さらなる向上にはより多くの負荷を要する段階です。この段階までくると疲労管理の観点からも分割法のほうがシンプルで実践しやすくなります。1週間分の総負荷量を稼ぐために、一回あたりのトレーニング時間がある程度長くなることも覚悟して行ってください。週4以下のトレーニング頻度であるだとか、疲労管理に自信がある方(ピーキングなどが上手い人)は全身法でも良いでしょう。先述の通り、結果的に総負荷量が大きくなるのはどちらかが判断のポイントです。
超級者
好きにしてください
ご自身に合った方法がすでに確立されていると思います。
こちらからオススメすることは特にありません。

私の場合は総負荷量が稼げそうだったので、もうしばらくは全身法でやってみようと思います。
実践してみる方は、くれぐれも疲労過多にはご注意ください。
今回は以上です、ご精読ありがとうございました。
- Schoenfeld BJ, Ratamess NA, Peterson MD, Contreras B, Tiryaki-Sonmez G. Influence of Resistance Training Frequency on Muscular Adaptations in Well-Trained Men. J Strength Cond Res. 2015 Jul;29(7):1821-9
- Franco CMC, Carneiro MAS, de Sousa JFR, Gomes GK, Orsatti FL. Influence of High- and Low-Frequency Resistance Training on Lean Body Mass and Muscle Strength Gains in Untrained Men. J Strength Cond Res. 2021 Aug 1;35(8):2089-2094.